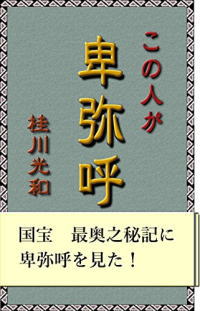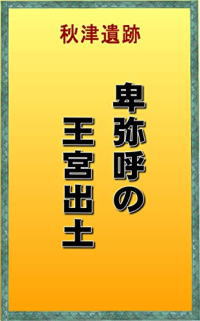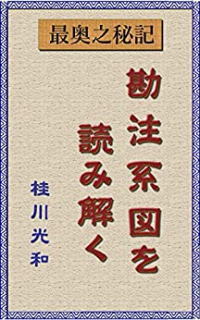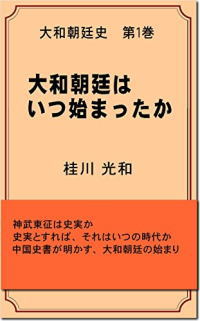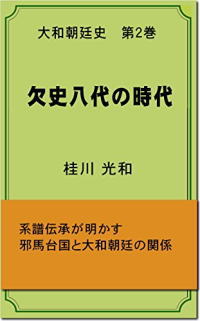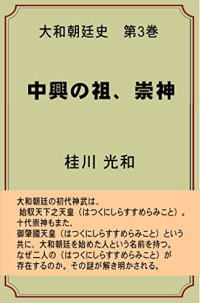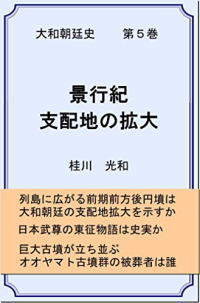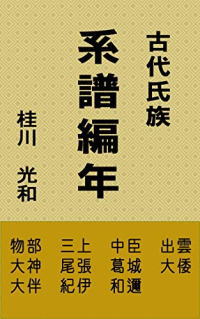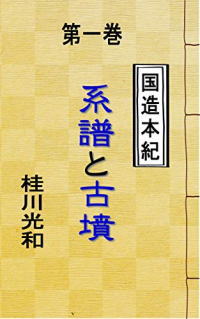この国の歴史教科書は、日本という国家の具体的な記述を、いきなり飛鳥時代から始める。それ以前は、古墳時代、弥生時代という時代区分で、考古学的記述を並べるだけである。なんとも唐突な国家の始まりである。
今日の日本につながる国が、いつ始まったのか何も教えてはくれない。
世界遺産に登録された、仁徳天皇陵の大きさは480mとされる。世界的に見ても巨大な墳墓である。このような巨大墳墓を造るには、国家としてのまとまりがなければ不可能である。飛鳥時代以前に国家が誕生している。
このホームページは、今日の学説の多くが、史実ではないと否定する『記紀』伝承の四世紀以前に実年代を与え、日本という国家の成り立ちを、明らかにしようとするものである。
今日に続く天皇家は、世界最長の皇室である。『日本書紀』は、天皇家の初代を神武天皇とする。神武が、後の大和朝廷に続く王権を打ち立てたのである。
『後漢書倭伝』は、西暦107年、倭国王が後漢王朝に朝見してきたことを伝える。中国史書に倭国が登場するのはこれが最初である。この倭国王こそ、大和朝廷の初代とされる神武に他ならない。そして『魏志倭人伝』が記す、邪馬台国とは「やまとの国」で、初期大和朝廷の事である。そのことを論証する。
きっとあなたの古代史観が変わる。
2021年2月19日 第1部、第2部、第3部公開
第1部 大和朝廷史
第1章 中国史書に見る五世紀史
第2章 朝鮮史書と対応する四世紀
- 神功皇后三韓征伐は史実か?
- 袴狭遺跡出土船団図
- 新羅侵攻は仲哀没年の翌年
- 早められた新羅出兵の年次
- 新羅本記に見る倭侵攻記事
- 日食が証明する新羅出兵の年次
- 疑問の多い応神の没年干支
- 応神天皇没年が出土遺物で解けた
第3章 卑弥呼と台与の時代
第4章 『後漢書倭伝』に見る倭国の歴史
第2部 卑弥呼の王宮と墓
卑弥呼の王宮
- 卑弥呼の王宮は秋津嶋宮
- 秋津島宮はどこ
- 伝承の地から出土した特異な建物群
- 竪穴建物が方形区画施設を切り崩す
- 炭素年代による高床式建物の年代
- 多孔銅鏃という二世紀から三世紀の遺物
- 庶民の持ち物ではない装身具
- 広い範囲から持ち込まれた土器
径百余歩卑弥呼の墓
第3部 『魏志倭人伝』に登場する人物
- 卑弥呼は宇那比姫命
- 男弟は六代孝安天皇
- 唯男子一人あり、飲食を給う
- 邪馬台国 4人の高官
- 倭国乱
- 遣使に立った人たち
- 台与擁立前の男王
- 孝元は孝霊の子ではない
- 台与は天豊姫
- 台与は開化の妃とされる竹野媛
- 丹波は大和朝廷の重要な支配地
- 狗奴国との戦い
第4部 邪馬台国探しは、なぜ混乱したか