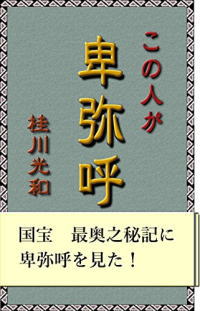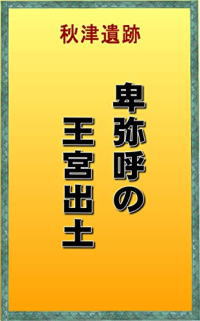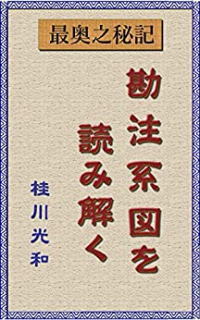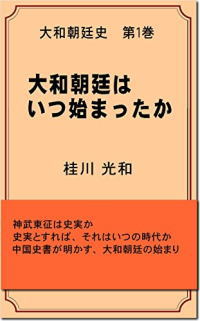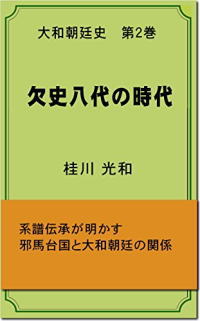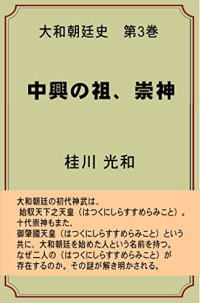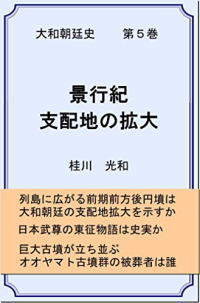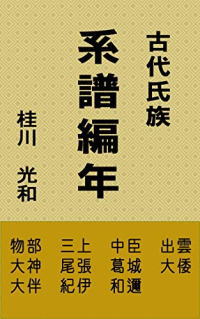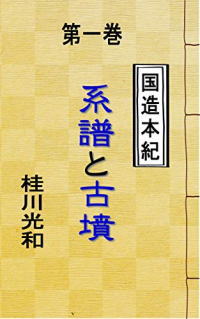冒頭の書き出しだけでもこれだけの違いがある
前者は『魏志倭人伝』、後者は『後漢書』倭伝の冒頭の書き出しである。
『魏志倭人伝』
倭人在帯方東南大海之中、依山島為国邑。旧百余国、漢時有朝見者、今使訳所通三十国。 従郡至倭、循海岸水行、歴韓国、乍南乍東、到其北岸狗邪韓国、七千余里・・・自郡至女王国万二千余里。
『後漢書』倭伝
倭在韓東南大海中、依山嶋為居、凡百余国。自武帝滅朝鮮、使駅通於漢者、三十許国、国皆称王、世世伝統。其大倭王居邪馬臺国。【案、今名邪摩(惟)堆、音之訛也。】楽浪郡徼、去其国万二千里、去其西北界狗邪韓国七千余里。
両者は重要な部分でまったく意味が異なる。
魏志は「(倭国は)もとは百余国、漢の時朝見する者有り、今使訳を通づるところ三十国」とする。これに対し『後漢書』は「(倭国は)おおよそ百国あまり、武帝が朝鮮を滅ぼしてより、漢に使駅を通づる者、三十国ばかり」とする。
『魏志倭人伝』は、今とするから魏の時代であろう。三十国もの国が通訳をともなって使者派遣してきたなどとは、とても信じられない。
これに対し『後漢書』倭伝は、武帝が朝鮮を滅ぼしてよりとする。前漢の武帝が朝鮮を滅ぼすのは、紀元前108年である、この時以来使者を派遣してきた国が三十国ばかりとする。これならありえる。
次の『魏志倭人伝』では「郡より女王国に至る万二千里あまり」とする、郡は帯方郡であり、距離推定の起点は、帯方郡である。これに対し『後漢書』倭伝も総距離は同じく万二千里とするが、距離の起点は、帯方郡ではなく楽浪郡なのである。 起点となる場所の名前が異なる。前者は後漢時代、後者は魏の時代の地名である。
さらに『魏志倭人伝』は帯方郡から、倭国の北岸にある狗耶韓国までを七千里とする。
これに対し『後漢書』倭伝は、倭の西北界にある句耶韓国を去ること七千里とする。まったく意味が異なる。
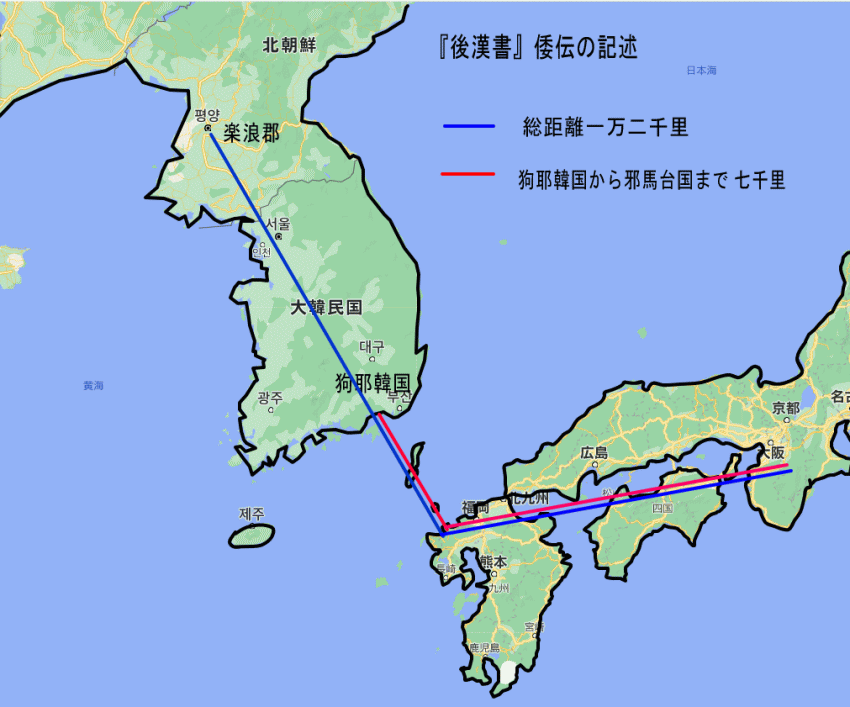
邪馬台国九州説を唱える人は『魏志倭人伝』の記述から、帯方郡から狗耶韓国までが七千里、狗耶韓国から末盧国までが三千里、すると残りは二千里で、邪馬台国が、九州島を出ることは無いと主張する。
だが『後漢書』倭伝に従えば、総距離は一万二千里で同じであるが、七千里は、倭国の対岸にある狗耶韓国から邪馬台国までである。
さらに次の一文は『魏志倭人伝』には見かけない記述である。
「国皆称王、世世伝統。其大倭王居邪馬臺国」
もし『後漢書』倭伝が、事実を伝えるものであれば、倭にはいくつかの国があり、それぞれに世襲的な、王があり、 その中の「大倭王」は邪馬台国に居たとする。 問題はこの「大倭」の意味である。
私が注目するのは、『魏志倭人伝』の伊都国についての記述で使われる「大倭」の語句である。『魏志倭人伝』は「国々市有りて、有無するところを交易す。大倭の使いこれを監す」とする。ここで「大倭」が唐突に登場する。これだけでは「大倭」の意味かまったく不明である。だが先の「国皆称王、世世伝統。其大倭王居邪馬臺国」という一文があれば、「大倭」の意味が解る。「大倭」とは「おおやまと」という国の名である。「大倭」の語句は、『魏志倭人伝』でも使われているから『後漢書倭伝』倭伝が、勝手に創作した語句ではない。原典に有った語句なのである。したがってこの一文も『後漢書』倭伝が勝手に付け加えたのではない。
また、この部分の「邪馬臺国」の「臺」は台であつて『魏志倭人伝』の「邪馬壹国」の「壹」すなわち壱ではないことも注目に値する。
このように『魏志倭人伝』と『後漢書』には、冒頭の百文字足らずで、これだけの違いがある。この後に続く文章も、語句や構成に微妙な差がある。
范曄が『魏志倭人伝』を改ざんしたとする、合理的な根拠は何も無い。 『後漢書』倭伝は『魏志倭人伝』からの派生ではないのである。ただし二つの史書が及言する共通部分には、高い類似性がある。無関係ではない。 同一の原典から派生したものである。 二つの史書が及言する部分については、『後漢書』倭伝の方が原典の意味を、より正確に伝えていると考える。
ここでは、このページに関係あるメッセージのみお願いします。
反論、批判、感想など何でも結構ですが、私の論拠や論理、主張に対してのみお願いします。関係ないメッセージは削除します。
第1部 大和朝廷史
第2章 朝鮮史書と対応する四世紀
- 神功皇后三韓征伐は史実か?
- 袴狭遺跡出土船団図
- 新羅侵攻は仲哀没年の翌年
- 早められた新羅出兵の年次
- 新羅本記に見る倭侵攻記事
- 日食が証明する新羅出兵の年次
- 疑問の多い応神の没年干支
- 応神天皇没年が出土遺物で解けた
第3章 卑弥呼と台与の時代
第4章 『後漢書倭伝』に見る倭国の歴史
著書