誰が描いた地理像か?
陸行一月の解釈を行なうにあたり、誰がどのようにして距離や方位を推定したかを考えてみる。
邪馬台国へ至る地理像を描いたのは、この間を実際に旅した人ではない。邪馬台国を訪れた、使者の報告書、あるいは紀行記を基に描かれた地理像である。そのためこの地理像は、とんでもない誤認と不正確さを持つている。その一例を示す。
末蘆国から伊都国間を陸行とする。だがこの間も船である。
なぜならその後、水行二十日、あるいは十日という長い船旅を控えこの間を、荷物を背負って歩くことなどあり得ない。
一支国すなわち壱岐から九州島を目指せば、松浦半島の北端に上陸する。現在の呼子あたりである。ここは末蘆国の一部である。ここから次の伊都国のある糸島半島は、目と鼻の先である。対馬海峡を渡ってきた船であれば、航行に何の問題もない。船を降りて、この間を陸行することなどあり得ない。
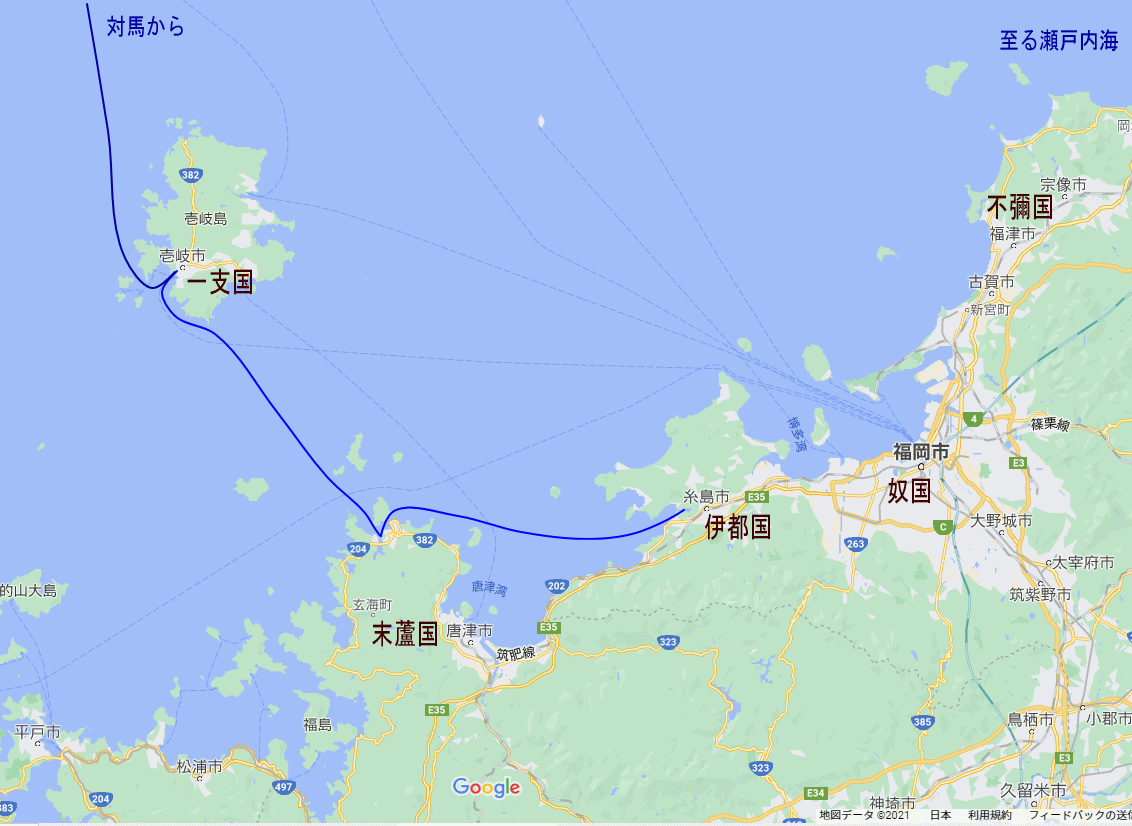
その証拠に魏志倭人伝は、伊都国について次のように記す。
「王遣使詣京都 帶方郡 諸韓國 及郡使倭國 皆臨津捜露 傳送文書 賜遣之物詣女王 不得差錯」
(女)王の遣使が(魏)の都に詣でたり、帯方郡、諸韓國の使が倭国に及ぶにあたり、皆津に臨み、伝送の文書や、女王への贈り物に間違いがないか開けて確認する。
「皆津に臨み」とするから港に寄るのである。港へは歩いてくるわけではない船で来るのである。
また『魏志倭人伝』は寄った国の官、すなわちそこの長について名前を記す。ところうが末蘆国のみ、この記述がない。末蘆国の中心部、現在の唐津市には立ち寄っていない。松浦半島の北端、呼子あたりから直接糸島半島の港を目指しているのである。
それではなぜ、この間を陸行とするのか。それは末蘆国についての次のような記事を誤解したのである。
「至末廬國 有四千餘戸 濱山海居 草木茂盛 行不見前人」この「草木茂盛 行不見前人」を移動の様子と誤解しているのである。
「草木茂盛 行不見前人」は前の文から続く情景の描写である。上陸地点の情景を描いたもので、移動の様子ではない。これを移動の様子と読み間違えたのである。
もし倭国を訪れた人が描いた地理像なら、こんな間違いをすることはない。
240年倭国を訪れた魏の使者の報告書、あるいは紀行記のようなものから、地理像を描いたのである。
もちろん伊都国以降も船旅で、最後の陸行一月以外は全行程水行である。
第4部 邪馬台国探しは、なぜ混乱したか