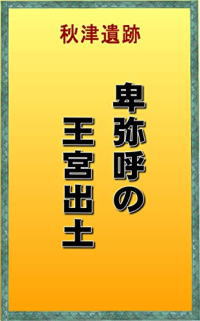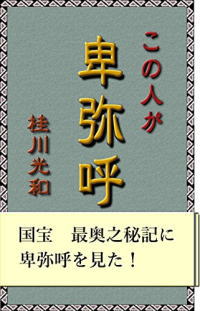広い範囲から持ち込まれた土器
西日本の瀬戸内海沿岸や東海地方など広い範囲から持ちこまれた土器が出土する。
ここが王都の場所であることを物語る。



発掘調査に当たった橿考研の担当者は、遺構の特殊性から大和朝廷が営んだ遺構とする。
だが『日本書紀』で、この葛城地方が登場するのは、初代神武の時代や、二代綏靖の葛城高丘宮、五代孝昭の掖上池心宮、六代孝安の室秋津島宮などである。何れも十代崇神以前で、崇神時代を300年前後とすれば、何れも古墳時代前期より前である。
秋津という地名の由来は、神武が秋津の南にある国見山で国見をする。この時、周りを山々が取り囲む様子がトンボの交尾する様子に似ることからトンボの古い呼び名であるアキツと名付けたとされる。奈良盆地南部のこのあたりは、大和朝廷発祥の地であり、初期の大和朝廷の宮が営まれた場所でもある。卑弥呼の時代もここに宮が置かれたのである。
私のブログ
ここでは、このページに関係あるメッセージのみお願いします。
反論、批判、感想など何でも結構ですが、私の論拠や論理、主張に対してのみお願いします。関係ないメッセージは削除します。
コメント欄を読み込み中
第2部 卑弥呼の王宮と墓
卑弥呼の王宮
- 卑弥呼の王宮は秋津嶋宮
- 秋津島宮はどこ
- 伝承の地から出土した特異な建物群
- 竪穴建物が方形区画施設を切り崩す
- 炭素年代による高床式建物の年代
- 多孔銅鏃という二世紀から三世紀の遺物
- 庶民の持ち物ではない装身具
- 広い範囲から持ち込まれた土器
径百余歩卑弥呼の墓