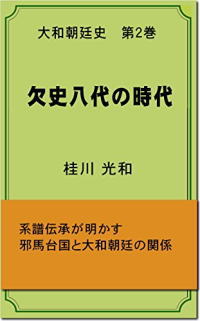航空写真にみる径百余歩の尾根
秋津遺跡の発掘調査が始まる二年前のことである。私は秋津島宮を探して初めて御所市を訪れた。
だが、地中に埋もれた秋津島宮は、歩き回っても容易に見つかるわけではない。
一方、卑弥呼は径百余歩の墓に葬られたとする。径とするから円墳であろう。一歩は1.44mで、百余歩はおおよそ150m前後であろう。これだけ巨大な円墳であれば、たとえ長い年月の間に、大きく形を変えようとも、必ず目に見える形で存在する。そのような確信のもと、秋津島宮の伝承地、室(むろ)の近辺を探し回った。見通しのきく平地なら、古墳を探すのは容易である。だが樹木に覆われた山中で、古墳を見つけるのは至難である。そこで航空写真を用いることにした。
秋津島宮伝承地である、室(むろ)の東、1㎞ほどの所に、玉手山という山がある。その山に円形の尾根を見た。古墳ではないかと踏査を行なった。

説明のために番号を付ける。左からNo1、No2、No3である。現地を訪れ、何れの尾根にも墳丘が存在することを確認した。後に判明するが、No3は遺跡地図で直径20mの円墳とするが、No1とNo2は、遺跡地図に掲載されていない古墳であった。尾根の形から遺跡地図にない古墳を2基発見したのである。
円形に見えるNo1の尾根は、右下に見える全長150mの掖上かんす塚古墳とほぼ同じ大きさである。

また、No1の尾根は、秋津島宮の方から眺めると巨大な土まんじゅうの形で、まさに径百余歩の円墳である。
日本列島では、直径150mの円墳は知られていない。これこそ卑弥呼の墓と考える。
ここでは、このページに関係あるメッセージのみお願いします。
反論、批判、感想など何でも結構ですが、私の論拠や論理、主張に対してのみお願いします。関係ないメッセージは削除します。
第2部 卑弥呼の王宮と墓
卑弥呼の王宮
- 卑弥呼の王宮は秋津嶋宮
- 秋津島宮はどこ
- 伝承の地から出土した特異な建物群
- 竪穴建物が方形区画施設を切り崩す
- 炭素年代による高床式建物の年代
- 多孔銅鏃という二世紀から三世紀の遺物
- 庶民の持ち物ではない装身具
- 広い範囲から持ち込まれた土器
径百余歩卑弥呼の墓