炭素年代による高床式建物の年代
高床式建物群の年代を推定する自然科学分析がある。橿原考古学研究書の2013年度調査報告書に、炭素年代測定値を記す。
橿考研は一世紀から三世紀頃について日本列島の資料を北半球の標準較正曲線で推定すると、実際より古い年代になるとして、暦年代の提示は行なっていない。確かにこのあたりの年代は実際より古い値が出るとされる。
しかしその誤差を見込んだとしても、高床式建物の一番古い年代を示す測定値は、古墳時代前期に収まるようなものではない。
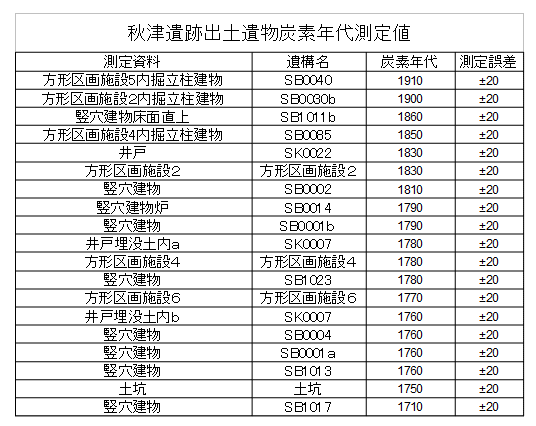
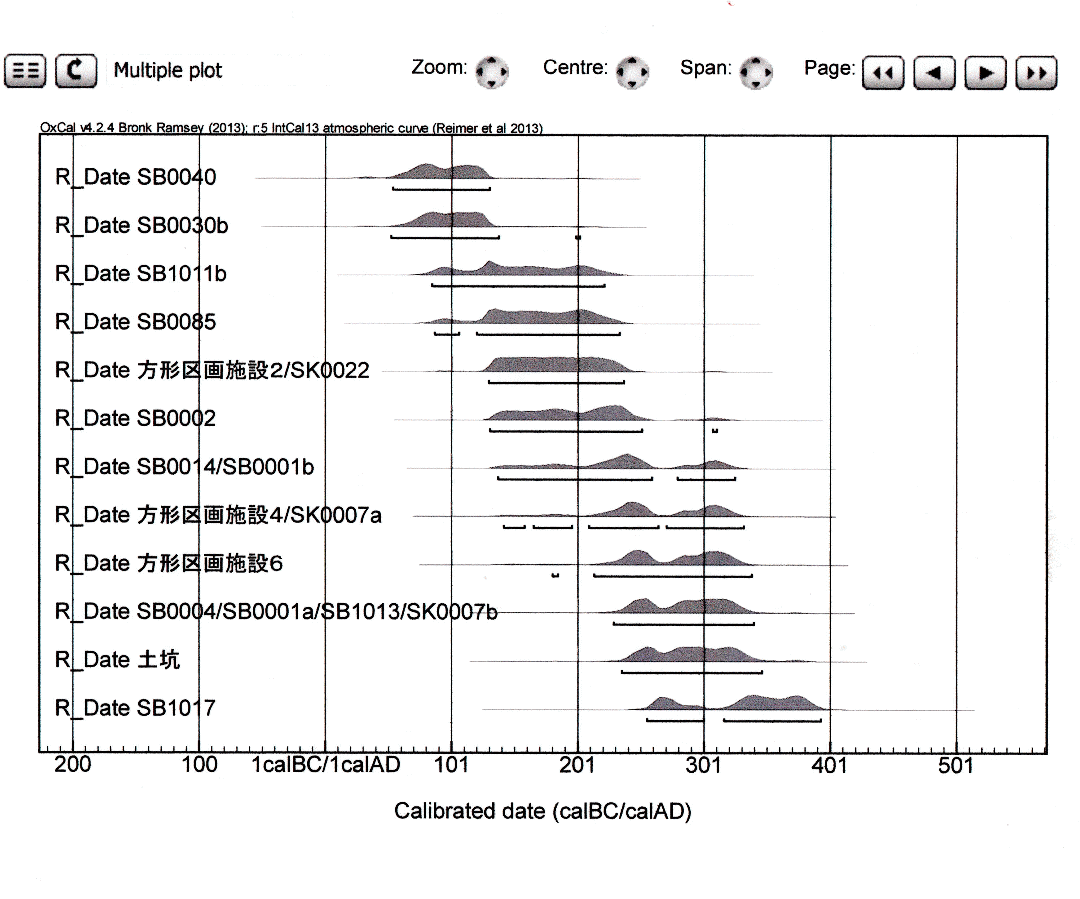
そこで私はオックスフォード大学が提供する、北半球の標準較正曲線を使い暦年代の推定を行なった。
次の図は、北半球の標準較正と南半球の標準較正曲線に、日本列産の年代の解る樹木から測定された、炭素年代測定値を重ねたものである。
白色が北半球、緑色が南半球、グレーが日本列島産樹木の炭素年代と暦年代との関係を表すグラフである。確かに一世紀から三世紀の間では、日本列島産の樹木の暦年代は、北半球の標準曲線から大きくずれる。この間を北半球の校正曲線で暦年代を推定するとざっと100年くらい古くなる。しかし200年も古くなるわけではない。
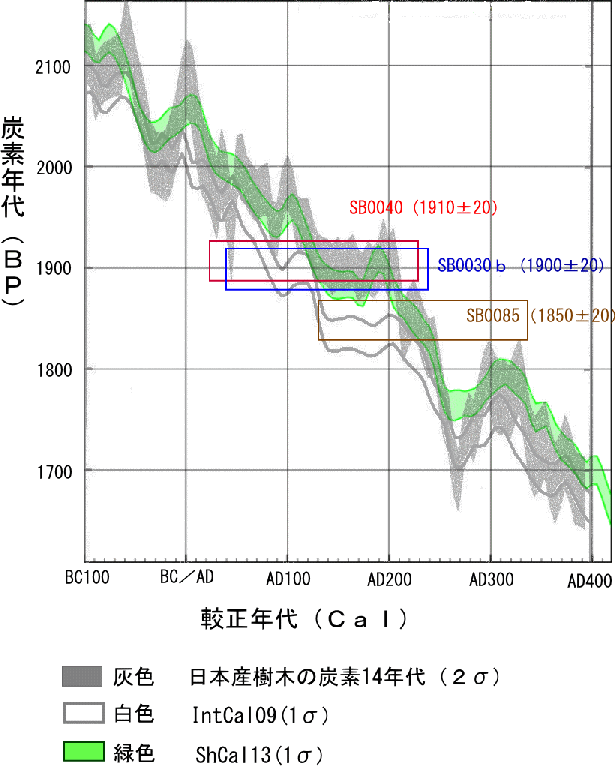
一世紀から三世紀中ごろに限れば、日本列島産の樹木の炭素年代測定値は、南半球の較正曲線の値に似る。そこで南半球の較正曲線ShCalでSB0040を校正したのが次のグラフである。
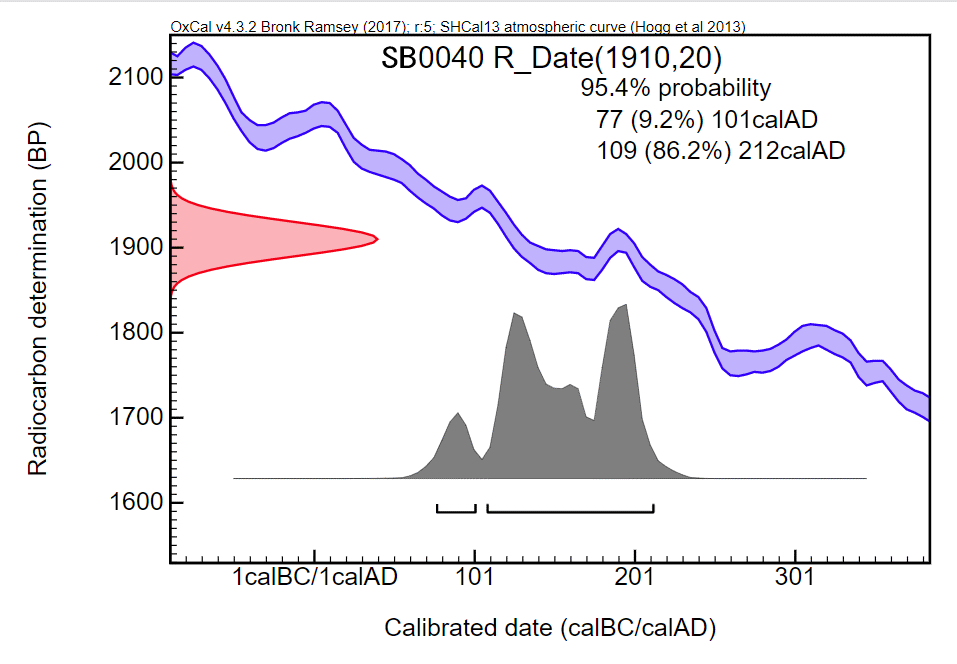
卑弥呼の在位年代の建物として矛盾はない。もちろんこれは、資料の年代であって、即建物の年代というわけではない。だが大きな違いはなかろう。
この高床式建物群は、卑弥呼の在位年代の物である。更にこの遺構が古墳時代前期以前にさかのぼると考えられる遺物が出土している。
ここでは、このページに関係あるメッセージのみお願いします。
反論、批判、感想など何でも結構ですが、私の論拠や論理、主張に対してのみお願いします。関係ないメッセージは削除します。
第2部 卑弥呼の王宮と墓
卑弥呼の王宮
- 卑弥呼の王宮は秋津嶋宮
- 秋津島宮はどこ
- 伝承の地から出土した特異な建物群
- 竪穴建物が方形区画施設を切り崩す
- 炭素年代による高床式建物の年代
- 多孔銅鏃という二世紀から三世紀の遺物
- 庶民の持ち物ではない装身具
- 広い範囲から持ち込まれた土器